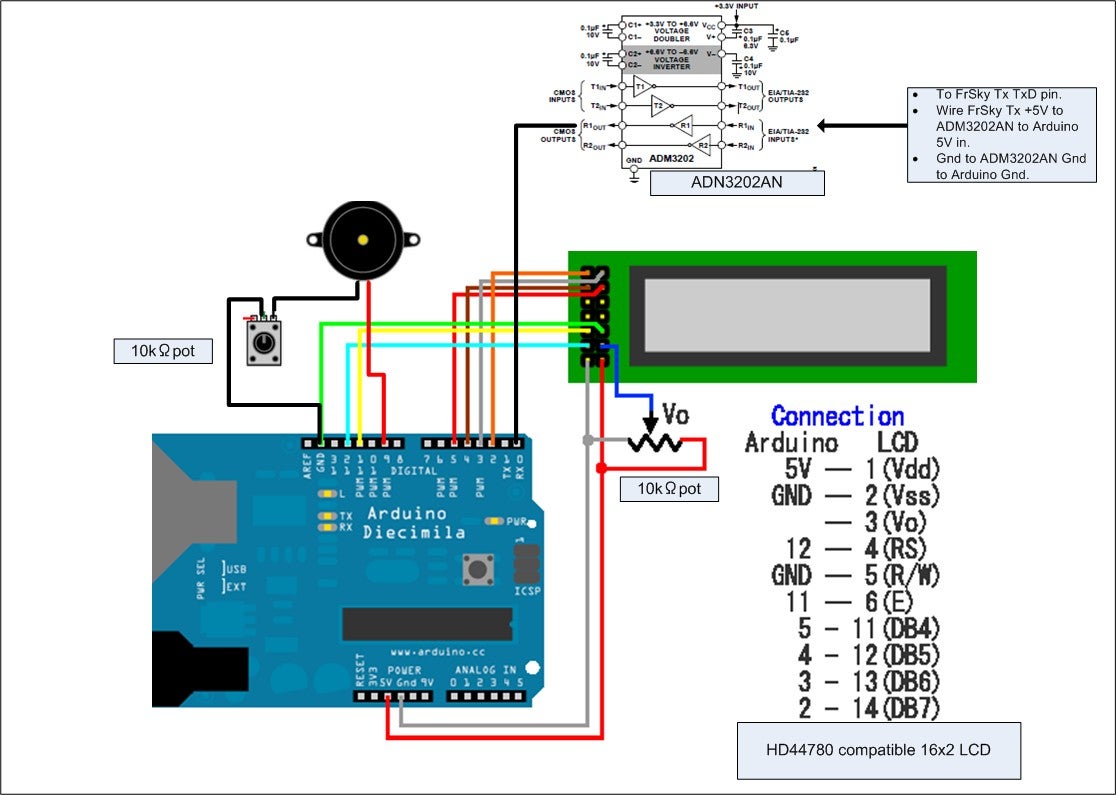FrSkyの電圧測定ポートA1, A2は3.3Vまでを1バイトの分解能で読み取ります。より高い電圧を測定するために分圧回路(divider)というものを使います。比例して電圧を変換するわけです。分圧回路の説明は
こちら。
測定する電圧によりその比を変えたくなります。私はFlytronの物を使っていますがこれは11:1、つまり3.3x11で最大36.3Vまで256の解像度で測定できます。最大8セルまで測定できますが0.14V刻みしかありません。
この分圧比が異なると同じ電圧でも異なる値になるので送信機の警告ブザーのレベル設定の変更やテレメトリデータの表示器の設定を変更する必要があります。
工場出荷時6:1。 2:1、4:1、6:1用端子が出ているのではんだ付けで切り替え可能

11:1固定です。

受信機に直接させるようになっておりA1、A2にそれぞれ4:1、11:1が割り当てられています。

受信機のモデルによる違い
FrSky社のTwo way シリーズにもいくつかの受信機が用意されており、モデルによりこのADポートの扱いが異なります。ユーザーの意見を反映しようとしているはいいことですが、その結果仕様がよく変わり安定しません。
8ch
現行モデルです。素直にA1, A2ポートとシリアルポートがついています。8chに1-8chをCPPMとしてまとめて出力する
D8RSPというファームウェアだけ違うモデルもあります。
テレメトリを使うならばこれが今のところ基本のモデルになります。受信機電圧を測定する場合は受信機ピンからYケーブルなどでプラスだけADポートにつなぎます。
国内で最初に認定されて際に販売されていたモデルです。A1ポートが内部的に4:1の分圧回路を通じて受信機電源につながっています。側面にはA2ポートとシリアルポートしか出ていません。
最初のを含めてD8Rのシリアルポートの真ん中のピンに5Vと記されていますがこれはミスプリ。送信したユーザデータの内容のシリアルデータが出力されいます。
最初に出てきた8ch受信機です。側面には素直にA1, A2ポート、シリアルポートが付いています。ファームウェアの書き換えは内部のピンから行っていました。ファームウェア書き換え用のアダプタも売られていますが、現在のD8R-IIでは不要です。
6ch
A1ポートは4:1の内部の分圧回路を通じて受信機電源に、A2ポートはサーボコネクタと並んで付いています。シリアルポートは付いていません。A1ポートは実際には6:1の分圧回路が載っていてソフトウェアで測定値を直しているという話もあります。(その場合分解能が落ちる。)
4ch
4ch受信機の形状をしていますが実際は1ch目に1-8chのCPPM信号を、2chピンにRSSI受信強度をPWMで出力するというFPVやマルチコプターで使う受信機となっています。Axポートがどうなっているのか、まだ出回っていないのでよくわかりません。^^;
電圧測定ポートの注意
グラウンドの扱い
動力用バッテリ、受信機電源などの電圧を測る場合グラウンドループを避けるためにマイナスは接続しないほうがよいです。プラス側だけ接続します。
オープンなとき
この点はまだ調査していないのですが、FrSkyのADポートは何も接続されていないときになにやら値を表示します。内部でプルアップ、プルダウンされていないからかもしれません。